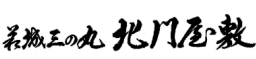世界遺産・萩城下町
萩の産業遺産群の構成要素として選定されている「萩城下町」は、萩城・旧上級武家地・旧町人町の3区域から成り、
幕末に産業化を目指した萩藩の地域社会を今に伝えています。
チェックイン後は、古地図を片手に、当時に想いを馳せながらの散策をお楽しみください。

※画像は横にスクロールしてご覧いただけます。
江戸時代:藩政の史跡巡り
1603年の関ケ原の戦いを経て、翌年、毛利輝元が築いた萩城を中心に始まった萩藩の藩政。
歴代藩主はこの地で実直な統治と学問の奨励に力を注ぎました。
藩校・明倫館では文武を磨く教育が行われ、質素倹約の中にも誠実さと理知を重んじる風土が根づいていきます。
幕末の変革を担う礎は、この静かな城下町で、二百五十余年をかけて静かに育まれていたのです。
萩城跡・武家屋敷エリア
-
萩城跡指月公園
徒歩約10分
萩城は慶長9年(1604)に毛利輝元が指月山麓に築城したことから、別名指月城とも呼ばれ、山麓の平城と山頂の山城とを合わせた平山城で、本丸、二の丸、三の丸、詰丸からなっていました。明治7年(1874)、天守閣、矢倉などの建物は全て解体され、現在は石垣と堀の一部が昔の姿をとどめ、一帯は国の史跡に指定されています。園内には天守閣跡、花江茶亭、梨羽家茶室、旧福原家書院、万歳橋、東園などの旧跡があり、春には県の天然記念物に指定されているミドリヨシノを始め、600本あまりのソメイヨシノが咲き誇ります。

-
萩城天守跡
徒歩約10分
萩城は天守、二の丸、三の丸を備えた壮大な城で、天守は桃山時代初期の様式を取り入れた5層の白い美しい建物でした。高さは約14.4m、基礎部分は東西19.8m、南北16.2mの規模でしたが、明治7年(1874)にすべて取り壊され、現在は礎石と台座だけが残っています。夜には天守跡の石垣などがライトアップされ、水面に映る幻想的な景色が楽しめます。

-
志都岐山神社
徒歩約10分
萩城跡・指月公園内にある志都岐山神社は、毛利元就から元徳まで萩藩歴代藩主を祀るかつての県社です。ふもとには、純白の花と緑のガクを持つ珍しい桜「ミドリヨシノ」が咲きます。遠目では淡い緑色に見えるのが特徴で、萩にしか咲かず、県の天然記念物に指定されています。

-
指月山
徒歩約25分
標高145mの指月山は“天然の要塞”と呼ばれ、萩城の詰丸が築かれて海と城内を監視していました。山麓には、寺社などが置かれていましたが、明治維新後すべて廃寺社となりました。山頂までは登山道があり、徒歩20~30分ほどで登れます。樹齢600年を超えるとされる巨樹が多く、希少な照葉樹林として国の天然記念物に指定されています。

-
花江茶亭
徒歩約10分
指月公園内にある風情ある茶室「花江茶亭」は、1854年頃に13代藩主・毛利敬親が別邸に建てたものです。幕末には、ここで家臣たちと時勢を語り国事を考えたといわれています。明治22年に現在の場所へ移築されました。茶室は茅葺きの木造平屋で、4畳半の本席と3畳の水屋から成り、後に控えの間が増築されました。

-
万歳橋
徒歩約10分
萩城本丸跡にある指月公園内の志都岐山神社前の庭池に架かる石橋で、もとは藩校明倫館にあったものを移築したものです。橋は花崗岩で造られており、長さ4.05m、幅員3.15mの直橋。橋脚はなく、両岸の石垣の橋台に2本のアーチ式橋桁を渡し、その上に10箇の短冊石を並べています。高欄の橋柱は左右5本ずつで、中国風のデザインを施した太鼓橋です。橋を渡る前の短冊石は失われ、現在は別の玄武岩の石が置かれています。

-
東園
徒歩約10分
東園は、指月公園の北東隅にある池の周囲一帯をさす、回遊式の庭園です。6代藩主毛利宗広の時代に古い池を整備し庭園とし、高台の建物から全体を見渡せるようにしたと伝えられています。7代藩主毛利重就もこの場所を憩いの場とし、園内に景観名を付けて風情を楽しみました。5月にはつつじが咲きます。
-
梨羽家茶室
徒歩約10分
指月公園内の花江茶亭の隣に位置する、毛利家の重臣・梨羽家の別邸茶室です。もとは上津江にあった梨羽氏の別邸に建てられていたもので、明治時代に移築されました。花江茶亭のような遊興の茶室ではなく、格式ある正式な座敷構えを持つ茶室で、木造桟瓦葺・入母屋造りの花月楼形式を今に伝える貴重な建物です。年末の城内大掃除の際、藩主が一時的に移る場として使われたことから「煤払いの茶室」とも呼ばれています。
-
旧厚狭毛利家萩屋敷長屋
徒歩約7分
厚狭毛利家は毛利元就の5男元秋を始祖とする毛利氏一門で、萩屋敷は約15,500m2の広大な敷地を誇っていたが、主屋などは明治維新後に解体され、安政3年(1856)に建てられたこの長屋のみが残りました。本瓦葺き入母屋造りで、現存する萩の武家屋敷の中では最も大きく、国の重要文化財に指定されています。昭和43年(1968)に解体修理が完成し、内部に当時の調度品などが展示してあります。

-
萩市堀内地区伝統的建造物群保存地区
城下町萩は毛利輝元が慶長13年(1608)に指月山に城を築き、町割を行ったことに始まります。萩城三の丸にあたるこの地区には藩の諸役所(御蔵元・御木屋・諸郡御用屋敷・御膳夫所・御徒士所)と、毛利一門をはじめとする大身の侍屋敷が建ち並んでいました。近世城下町の侍屋敷としての地割をよく残し、土塀越しにみえる夏蜜柑とともに歴史的景観を形成している点に高い価値が認められています。

-
本町(御成道)
萩城三の丸は藩内でも最上級の武士の居住地で、城下の侍屋敷と比べてもその屋敷地の広さが際立っています。中でも藩主の通るお城から中の総門までの御成道・本町沿いには毛利一門や家老などの重臣の屋敷が建ち並び、当時の道幅は現在の約2倍もありました。

-
問田益田氏旧宅土塀
徒歩約2分
永代家老益田家の分家筋にあたる問田益田氏旧宅の土塀。旧三の丸に位置し、高い土塀を巡らした重臣たちの屋敷が建ち並んでいた所で、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、今でも土塀が数多く残っています。特に、この土塀は231.7mと長く、往時の姿を最もよくとどめています。

-
口羽家住宅
徒歩約6分
口羽家は毛利氏の庶流で、もとは石見国巴智郡口羽村を領した要路城主でしたが、関ヶ原の戦いのあと毛利氏に従って萩に移り、萩藩寄組1,018石余として代々萩城三の丸に住みました。口羽家住宅は主屋と表門が揃って残る貴重なもので、表門は江戸藩邸の門を拝領して萩に移築したと伝えられています。また、主屋の座敷からは庭越しに橋本川の流れを眺めることができます。

-
堀内鍵曲
徒歩約8分
高い土塀で囲み道を鍵手形(クランク状)に曲げることで、行き止まりに見せかけたり見通しをきかなくした通り。城下に侵入した敵を迷わせ追い詰めるために作られたもので、別名「追い廻し筋」とも呼ばれます。

-
古明倫館跡
徒歩約6分
明倫館は萩藩5代藩主・毛利吉元によって享保4年(1719)に創建された藩校。江戸末期には270余を数えた藩校のうち12番目にできたもので、毛利氏の学問を重視する家柄がうかがえます。
-
旧益田家物見矢倉
徒歩約10分
萩藩永代家老益田家(12,063石余)の屋敷跡にあり、高さ1.8mの石塁の上に建ち、北の総門近くにあって物見(見張り)を兼ねていたため物見矢倉と呼ばれました。益田氏はもともと益田七尾城主でしたが、関ヶ原の戦いの後、徳川からの誘いを断り、報恩のある毛利氏について萩藩へ移住しました。これに感激した毛利輝元は益田家を毛利一門とし、萩藩永代家老をもって処遇しました。幕末の当主・益田親施は禁門の変の責を負って切腹した三家老の一人です。

-
旧周布家長屋門
徒歩約8分
周布家は萩藩大組士筆頭で、石見国周布郷の地頭職として周布村に居住していたことから周布を名乗りました。北の総門通りにある長屋門は江戸時代中期の代表的な武家屋敷長屋の様式です。

-
旧繁沢家長屋門
徒歩約10分
繁沢家(1,914石余)は阿川毛利家(7,300石)の分家で萩藩寄組に属していました。藩政初期の当主・繁沢就充は藩の要職として活躍しました。

-
天樹院墓所
徒歩約4分
萩藩祖・毛利輝元の墓所。慶長5年(1600)の関ヶ原の合戦に敗れ萩へ移った輝元は、ここにあった「四本松邸」を隠居所としました。輝元の死後、天樹院という菩提寺が建てられましたが維新後に廃寺になりました。竹林に囲まれた静かな場所に五輪塔形の墓が残っています。

-
北の総門
徒歩約10分
藩政時代に城下から城内・三の丸に入るために設けられた3つの門のひとつで、このほかに「中の総門」「平安古の総門」がありました。かつては門番が常駐して人の出入りを監視し、暮れ六つから明け六つまでは門が閉じられ、鑑札を持ったもの以外の通行を禁止していました。日本最大級の高麗門で、現在の門は平成16年に萩開府400年を記念して復元されたものです。

-
萩城外堀
徒歩約10分
萩城外堀萩城は本丸、二の丸、三の丸によって形成され、それぞれ内堀、中堀、外堀で防備されていました。外堀は城内と城下を隔てる堀で、当時は通行できる場所は3カ所しかなく、それぞれに門が設けられ厳重な警備がなされていました。

-
旧毛利家別邸表門
徒歩約1分
明治時代、14代藩主・毛利元徳が鎌倉材木座に建てました。大正10(1921)年の移築を経て、昭和49(1974)年に現在地に移築されました。桁行10.9メートル、梁間3.8メートル、棟高5.2メートルの雄大な規模で、屋根の両端には鯱の原型と言われる鴟尾(しび)を乗せた桟瓦葺寄棟造となっています。門の左側は潜門で、更に両脇には内側に向かって覗格子を持たせた10平方メートルの広さを持つ土間が付属する、萩の門の形式としては異色の表門です。

-
春日神社
徒歩約9分
1200年の歴史をもつ古社です。時代によって場所や祀官を変遷しながら、萩のまちを見守ってきました。安永2(1773)年に萩の大火により被害を受けたましたが、その翌年に毛利重就公により再建されたのが現在の社殿になります。
-
旧福原家萩屋敷門
徒歩約1分
萩藩永代家老・福原家(11,314石余)の萩上屋敷の表門。福原家の領地は宇部ですが、当主は代々毛利家の重臣として萩に住みました。建立は江戸中期と推定され、萩に現存する武家屋敷の門の中では珍しい、門番所のない形式です。幕末の当主・福原越後は、元治元年(1864)の禁門の変の敗戦後、長州藩が幕府への恭順を示すため、責を負って切腹させられた三家老の一人です。

城下町エリア
-
菊屋横町
徒歩約10分
「日本の道100選」にも選定された、白いなまこ壁が美しい横町です。藩の豪商・菊屋家をはじめ、幕末の風雲児・高杉晋作の誕生地や、第26代総理大臣・田中義一の誕生地があります。

-
江戸屋横町
徒歩約13分
維新の三傑の一人である木戸孝允の旧宅や、蘭方医・青木周弼の旧宅、高杉晋作・伊藤博文ゆかりの円政寺などが並ぶ、黒板塀の風情ある横町です。

-
-
菊屋家住宅
徒歩約10分
萩藩で御用達を勤めた豪商菊屋家の住宅で、その屋敷は幕府巡見使の宿として本陣にあてられました。屋敷地には数多くの蔵や付属屋が建てられているが、主屋、本蔵、金蔵、米蔵、釜場の5棟が国の重要文化財に指定されています。この住宅は、主屋が極めて古く、全国的にみても最古に属する大型の町屋としてその価値は極めて高いものです。菊屋家に伝わる500点余りの美術品、民具、古書籍等が常設展示されており、往時の御用商人の暮らしぶりが偲ばれます。

-
熊谷美術館・熊谷家住宅
徒歩約17分
熊谷家は萩藩の御用商人として栄えた豪商です。初代五右衛門芳充は1754年に藩主毛利重就に抜擢され、1768年に現在の熊谷家住宅を建てました。代々藩に仕え、明治以降も子孫が住み続けています。敷地内には国の重要文化財である主屋や蔵などがあり、熊谷美術館として約3000点の美術工芸品や古文書を展示。中でも最古のピアノとして知られる英国製スクエアピアノが有名です。
-
金毘羅社 円政寺
徒歩約15分
真言宗月輪山円政寺は大内氏代々の祈願寺として建立されたもので、毛利氏の萩築城の折に萩に移築されました。入口には神仏混淆を示す鳥居があり、境内の金比羅社には幼少の高杉晋作が度胸試しをした大天狗の面が掲げられています。伊藤博文も11歳のときこの寺に預けられて雑用の傍ら読み書きを習いました。今でもその頃使用した煉瓦の硯や背負子などが残されています。

松陰神社・東萩駅エリア
-
東光寺
車で約13分
元禄4年(1691)に、萩藩3代藩主である毛利吉就が創建した全国屈指の黄檗宗(おうばくしゅう)の寺院で、大照院とならぶ毛利家の菩提寺です。総門、三門、鐘楼、大雄宝殿はいずれも国の重要文化財に指定されています。毎年8月15日には「萩・万灯会」が行われ、送り火では約500基の石灯篭に灯が入り、まさに幽玄の世界が広がります。

その他
-
大照院
車で約7分
もとは臨済宗南禅寺派の寺院で、荒廃していたものを、萩藩2代藩主である綱広が承応3年(1654)から明暦2年(1656)にかけて再建した菩提寺です。5月上旬には藤の花が甘い香りと彩りを添え、毎年8月13日に行われる「萩・万灯会」の迎え火では、約600基の石灯篭に灯が入り、幽玄の世界が広がります。

幕末:志士の史跡巡り
揺らぐ幕藩体制の中で、長州藩は内なる改革に踏み出し、討幕の志を胸に、時代の矢となる決意を固めていきます。
吉田松陰——若くして命を懸けて学び、伝え、未来を託した人。
彼が開いた松下村塾では、若き命がぶつかり合い、言葉が火花のように飛び交っていたのです。
その熱は、やがて高杉晋作の行動となり、木戸孝允の知恵となり、明治という新しい時代を動かしていきます。
石垣に、白壁に、ふとした風の中に、ふり向くと松陰のまなざしと志士たちの熱が、
今もこの町にそっと残されているように感じられます。
萩城跡・武家屋敷エリア
-
旧福原家萩屋敷門
徒歩約1分
萩藩永代家老・福原家(11,314石余)の萩上屋敷の表門。福原家の領地は宇部ですが、当主は代々毛利家の重臣として萩に住みました。建立は江戸中期と推定され、萩に現存する武家屋敷の門の中では珍しい、門番所のない形式です。幕末の当主・福原越後は、元治元年(1864)の禁門の変の敗戦後、長州藩が幕府への恭順を示すため、責を負って切腹させられた三家老の一人です。

城下町エリア
-
高杉晋作誕生地
徒歩約10分
幕末の風雲児・高杉晋作は、天保10年(1839)に毛利家に代々仕えた藩士高杉家の長男として生まれ、7歳から藩校明倫館へ、19歳で松下村塾に入塾し松陰の影響を強く受けました。文久3年(1863)には身分に因らない画期的な軍「奇兵隊」を結成。禁門の変後の長州征伐が迫るなかで藩内に台頭していた佐幕派を排斥し藩論を倒幕へ統一しました。第二次長州征伐でも海軍総督として幕府艦隊を退けるなど活躍し、長州藩を勝利へ導きましたが、慶応3年(1867)、維新を目前に結核のため27歳の生涯を閉じました。現在生家は個人所有となっていますが、縁側や玄関先から写真や書などの展示を見学することができます。

-
木戸孝允旧宅
徒歩約13分
木戸孝允は天保4年(1833)藩医・和田昌景の長男として生まれ8歳で藩士・桂家の養子となりますが、養父母が早くに亡くなったため江戸に出るまでの約20年間をこの実家で過ごしました。17歳のとき明倫館で松陰に学び、20歳で江戸に遊学、30歳の頃から藩の要職につく一方、京都に赴いて国事に奔走しました。慶応2年(1966)、薩摩藩の西郷隆盛らと薩長連合を結び、明治新政府では五箇条の誓文の確定に参画し、版籍奉還、廃藩置県の実現に尽力。これらの功績により「維新の三傑」と呼ばれます。誕生の部屋や庭園などよく旧態を残しており、幼少時代の書の展示なども見ることができます。

-
青木周弼旧宅
徒歩約15分
13代藩主・毛利敬親の侍医を務めた青木周弼の旧宅。幕末当時、日本屈指の蘭方医でもありました。来客用と家人用の座敷に分けられた母屋が、全国から門下生が集まった青木家の事情を物語っています。

-
旧久保田家住宅
徒歩約10分
久保田家は初代庄七が江戸時代後期に近江から萩に移って呉服商を開き、2代目の庄次郎から酒造業に転じたと伝えられています。明治時代には来萩した名刺の宿所としてもしばしば利用されました。現在はボランティアガイドが常駐し、施設は様々なイベントの拠点としても使用されています。

-
菊屋家住宅
徒歩約10分
萩藩で御用達を勤めた豪商菊屋家の住宅で、その屋敷は幕府巡見使の宿として本陣にあてられました。屋敷地には数多くの蔵や付属屋が建てられているが、主屋、本蔵、金蔵、米蔵、釜場の5棟が国の重要文化財に指定されています。この住宅は、主屋が極めて古く、全国的にみても最古に属する大型の町屋としてその価値は極めて高いものです。菊屋家に伝わる500点余りの美術品、民具、古書籍等が常設展示されており、往時の御用商人の暮らしぶりが偲ばれます。

-
熊谷美術館・熊谷家住宅
徒歩約17分
熊谷家は萩藩の御用商人として栄えた豪商です。初代五右衛門芳充は1754年に藩主毛利重就に抜擢され、1768年に現在の熊谷家住宅を建てました。代々藩に仕え、明治以降も子孫が住み続けています。敷地内には国の重要文化財である主屋や蔵などがあり、熊谷美術館として約3000点の美術工芸品や古文書を展示。中でも最古のピアノとして知られる英国製スクエアピアノが有名です。
-
金毘羅社 円政寺
徒歩約15分
真言宗月輪山円政寺は大内氏代々の祈願寺として建立されたもので、毛利氏の萩築城の折に萩に移築されました。入口には神仏混淆を示す鳥居があり、境内の金比羅社には幼少の高杉晋作が度胸試しをした大天狗の面が掲げられています。伊藤博文も11歳のときこの寺に預けられて雑用の傍ら読み書きを習いました。今でもその頃使用した煉瓦の硯や背負子などが残されています。

松陰神社・東萩駅エリア
-
松下村塾
車で約12分
吉田松陰の志を継ぐ維新志士たちを数多く輩出した私塾です。天保13年(1842)に松陰の叔父である玉木文之進が自宅で私塾を開いたのが始まりで、安政4年(1857)に28歳の松陰がこれを継ぎ、主宰することになりました。わずか1年余りの間でしたが、久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文、山県有朋、山田顕義、品川弥二郎など、明治新政府に活躍した多くの逸材を育てました。

-
松陰神社
車で約12分
明治40年(1907)に創建された、吉田松陰を祭神とする神社です。学問の神として信仰が厚く、境内には松陰ゆかりの史跡などが点在しています。

-
吉田松陰の墓及び墓所
車で約12分
吉田松陰の墓は、松陰誕生地に隣接した、団子岩とよばれる風光明媚な場所に建っています。松陰の没後100ヵ日にあたる万延元年(1860)2月7日に遺髪を埋葬、同月15日に松陰の墓碑を建立しました。この墓所には、杉百合之助、吉田大助、玉木文之進、久坂玄瑞など一族の墓のほか、門人の高杉晋作などの墓もあります。

-
伊藤博文旧宅
車で約12分
伊藤博文は、天保12年(1841)に熊毛郡束荷村(現在の山口県光市)の農家に生まれました。この旧宅は、もとは萩藩の中間 伊藤直右衛門の居宅でしたが、安政元年(1854)に伊藤博文の父・林十蔵が伊藤家の養子となったため、一家をあげて伊藤家に入家。その後、博文が明治元年(1868)に兵庫県知事に赴任するまでの本拠となった家です。

-
伊藤博文別邸
車で約12分
伊藤博文が明治40年(1907)に東京府下荏原郡大井村(現:東京都品川区)に建てた大邸宅から、往時の面影をよく残す一部の玄関、大広間、離れ座敷の3棟を萩市に移築した別邸です。明治時代の宮大工伊藤万作の手によるもので、樹齢約1000年の吉野杉を使った大広間廊下の鏡天井や、離れ座敷の節天井など、非常に意匠に優れています。

萩城跡・武家屋敷エリア
-
萩八景遊覧船乗り場
徒歩約5分
12人乗りの小舟で水上観光が楽しめる萩八景遊覧船。萩城跡入口の指月橋をスタートし、堀内伝統的建造物群保存地区、白壁と川沿いの松並木などを眺めながらの遊覧は、陸上とはまた違った風情があります。桜の季節の【桜観賞コース】も人気です。

-
萩博物館
徒歩約7分
近世都市遺産の町並みや市内に数多くある文化財、史跡などを結びつける「まちじゅう博物館」の中核施設として2004年11月に開館。収蔵資料7万点の保存・展示、高杉晋作の遺品を公開します。

-
菊ヶ浜
徒歩約10分
北長門海岸国定公園内に位置し、萩城跡から浜崎商港まで延々と続く白砂青松の美しい海岸で水質も良好です。砂浜からは、国指定史跡萩城跡を望むこともでができます。また沖合いには笠山や、大島・相島など多くの島々を眺めることができ、日本の夕陽百選にも選ばれるほどのすばらしい景観を誇っています。

城下町エリア
-
田中義一誕生地
徒歩約10分
第26代内閣総理大臣 田中義一の生誕地です。田中義一は、元治元年(1864)に藩士・田中信祐の三男として生まれました。陸軍大学校を卒業し、日清戦争出征後、軍事情勢の探索のためロシアに留学。日露戦争では満州軍参謀として出陣しました。大正10年には陸軍大将となり、大正14年に政界入り、昭和2年(1927)に内閣総理大臣となりました。昭和3年に張作霖爆殺事件が勃発し、翌年の昭和4年、責任を問われて総辞職しました。
-
山口県立萩美術館・浦上記念館
徒歩約17分
萩出身の実業家・浦上敏朗氏のコレクションをもとに、平成8年に開館した浮世絵版画と東洋陶磁器を専門とする美術館。浮世絵約5,200点、東洋陶磁約500点、陶芸約750点(平成23年現在)を所蔵し、平成21年に発行された旅行ガイドブック「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」では2つ星の観光施設として掲載されました。歌川広重、葛飾北斎、歌川国芳らの浮世絵約5,200点ほか、中国・朝鮮の陶磁器や近現代の陶芸作品を収蔵展示しています。平成22年には「陶芸館」がオープンし、萩焼などの陶芸作品を展示するほか、江戸時代から現代に至る萩焼の歴史を資料や映像で紹介しています。